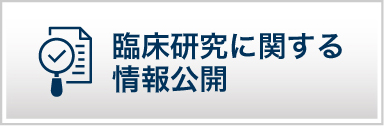Research / Equipment
研究と設備
研究者紹介
附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター
創薬スクリーニングユニット
坂本 潤一特任准教授(常勤)
製薬企業及び創薬支援CROにて培った、創薬ステージにおけるターゲット選定、アッセイ系構築、化合物スクリーニング(HTS)及び合成展開における化合物評価の経験及び知識を活用し、アカデミア創薬の一助になることを目指しています。
職歴:
1992.04-2017.06 武田薬品工業株式会社
2017.07-2024.06 Axcelead Drug Discovery Partners 株式会社
2024.07- 大阪大学大学院薬学研究科化合物ライブラリー・スクリーニングセンター
学歴:
1992.03 修士(農学)九州大学
2018.03 博士(生物科学)筑波大学
研究テーマ
化合物ライブラリーを用いたハイスループットスクリーニング(HTS)支援
化合物スクリーニングの重要な点は、選択した化合物が真にターゲットに作用していることをカウンターアッセイやコンファメーションアッセイにより確認したヒット化合物を取得することと考えています。このような化合物の取得を目指されているアカデミアの先生方が、より良いヒット化合物を取得するためのスクリーニングカスケードをご提案します。また、必要があれば、スクリーニング系の構築およびハイスループットスクリーニングを実施し、スクリーニングを全般的に支援します。
化合物ライブラリー提供支援
より良いヒット化合物を取得するために、化合物スクリーニングの目的に合ったライブラリーを選択することは重要です。当創薬サイエンス研究支援拠点が保有するJ-PUBLIC化合物ライブラリー、製薬企業オリジナルライブラリー、大阪大学オリジナル化合物ライブラリー、Drug-like、Pharmacological Diversity setを含む市販化合物ライブラリーより、ヒット化合物取得の可能性が高いライブラリーを選定し、ご提案・ご提供します。
Hit to Leadにおけるフォローアップ支援
これまでに培った知識や経験をもとに、ヒット化合物のMOA確認や類縁体評価などをご提案します。さらに、ヒット化合物の中からリード化合物候補を選定するストラテジーを当拠点の構造展開ユニットと協同で、ご提案し、支援します。
創薬研究機器利用支援
化合物ライブラリー・スクリーニングセンターは、創薬研究のための、ハイスループットスクリーニングや化合物評価アッセイを実施可能な様々な測定機器及び分注機器を設置しており、消耗品分の利用負担のみで、企業、アカデミア、非営利団体の皆様のご利用を支援します。
代表的な業績
Identification of novel inhibitors of Keap1/Nrf2 by a promising method combining protein-protein interaction-oriented library and machine learning
Y Shimizu, T Yonezawa, J Sakamoto, T Furuya, M Osawa, K Ikeda
Sci Rep. 2021 Apr 1;11(1):7420.
Discovery of an Irreversible and Cell-Active BCL6 Inhibitor Selectively Targeting Cys53 Located at the Protein-Protein Interaction Interface
T Sameshima, T Yamamoto, O Sano, S Sogabe, S Igaki, K Sakamoto, K Ida, M Gotou, Y Imaeda, J Sakamoto, I Miyahisa
Biochemistry. 2018 Feb 27;57(8):1369-1379.
Identification and Characterization of a New Series of Ghrelin O-Acyl Transferase Inhibitors
M Yoneyama-Hirozane, K Deguchi, T Hirakawa, T Ishii, T Odani, J Matsui, Y Nakano, K Imahashi, N Takakura, I Chisaki, S Takekawa, J Sakamoto
SLAS Discov. 2018 Feb;23(2):154-163.
Discovery of a Kelch-like ECH-associated protein 1-inhibitory tetrapeptide and its structural characterization
S Sogabe, K Sakamoto, Y Kamada, A Kadotani, Y Fukuda, J Sakamoto
Biochem Biophys Res Commun. 2017 May 6;486(3):620-625.
High-Throughput Quantitative Intrinsic Thiol Reactivity Evaluation Using a Fluorescence-Based Competitive Endpoint Assay
T Sameshima, I Miyahisa, S Yamasaki, M Gotou, T Kobayashi, J Sakamoto
SLAS Discov. 2017 Oct;22(9):1168-1174.
Novel DOCK2-selective inhibitory peptide that suppresses B-cell line migration
K Sakamoto, Y Adachi, Y Komoike, Y Kamada, R Koyama, Y Fukuda, A Kadotani, T Asami, J Sakamoto
Biochem Biophys Res Commun. 2017 Jan 29;483(1):183-190.
Discovery of high-affinity BCL6-binding peptide and its structure-activity relationship
K Sakamoto, S Sogabe, Y Kamada, N Sakai, K Asano, M Yoshimatsu, K Ida, Y Imaeda, J Sakamoto
Biochem Biophys Res Commun. 2017 Jan 8;482(2):310-316.
A new class of non-thiazolidinedione, non-carboxylic-acid-based highly selective peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) γ agonists: design and synthesis of benzylpyrazole acylsulfonamides
K Rikimaru 1, T Wakabayashi, H Abe, H Imoto, T Maekawa, O Ujikawa, K Murase, T Matsuo, M Matsumoto, C Nomura, H Tsuge, N Arimura, K Kawakami, J Sakamoto, M Funami, CD Mol, GP Snell, KA Bragstad, B Sang, DR Dougan, T Tanaka, N Katayama, Y Horiguchi, Y Momose
Bioorg Med Chem. 2012 Jan 15;20(2):714-33.
A novel oxyiminoalkanoic acid derivative, TAK-559, activates human peroxisome proliferator-activated receptor subtypes
J Sakamoto, H Kimura, S Moriyama, H Imoto, Y Momose, H Odaka, H Sawada
Eur J Pharmacol. 2004 Jul 8;495(1):17-26
Activation of human peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) subtypes by pioglitazone
J Sakamoto, H Kimura, S Moriyama, H Odaka, Y Momose, Y Sugiyama, H Sawada
Biochem Biophys Res Commun. 2000, Nov 30;278(3):704-11.